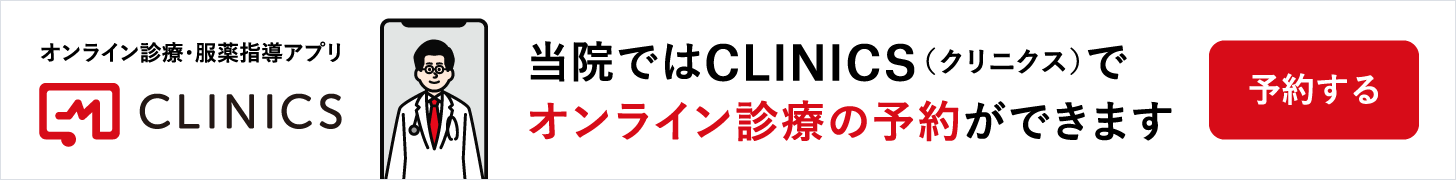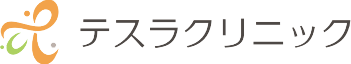ADHDの診断ってどうするの?実際の流れを解説します
2025.04.07
「もしかしてADHDかもしれない」
「集中できず、ミスが多いことがずっと気になっている」
「子どものことで学校から指摘を受けた」
そんな悩みをきっかけに、当院には日々多くのご相談が寄せられています。
今回は、「ADHDの診断って実際にどう進めるの?」というご質問にお答えし、当院での基本的な流れをご紹介します。
① 予約と問診票の記入
当院では、初診前にオンラインで問診票をご記入いただいています。
問診票では、これまでの生活や現在の困りごと、過去の診断歴などをお伺いします。これにより、初診時からより具体的なご相談が可能になります。
② 初診(医師による診察)
初診では、今のお困りごとや生活の状況、これまでの経過などを丁寧にお聞きします。
特に以下のような点を確認します:
- 幼少期から現在までの行動傾向
- 忘れ物や遅刻、ケアレスミスの頻度
- 周囲からの指摘や対人関係の困難
- 学校・職場での適応の様子
必要に応じて、家族や関係者からの情報、通知表、既往歴なども参考にさせていただきます。
③ スクリーニング検査の実施
ADHDの診断にあたっては、DSM-5という診断基準に基づいて評価を行いますが、補助的に以下のような質問票・検査も使用しています:
- ASRS(Adult ADHD Self-Report Scale):成人のADHD傾向を評価する質問票
- AQ(Autism-Spectrum Quotient):ADHDと重なりやすい自閉スペクトラム傾向を評価
- WAIS / WISC:必要に応じて、認知特性を確認するための知能検査を実施することもあります(実施は主に2回目以降)
検査の有無や内容は、医師と相談しながら個別に決定します。
④ 診断と方針のご説明(暫定診断について)
ADHDの診断は、問診・検査・情報の総合判断で行いますが、初診時点では情報が不十分なことも多いため、当院では**「ADHDの可能性が高い(=暫定診断)」という形で様子を見ながら判断を進める場合があります**。
焦らず慎重に、「今の困りごとにどう対応できるか?」を一緒に考えることを大切にしています。必要に応じて、診断の精度を高めるために追加の情報提供や診察をお願いすることもあります。
⑤ 支援・治療の選択肢
診断の結果に応じて、以下のような方法を検討します:
- 薬物療法:症状や生活背景に応じて検討します。当院で対応が難しい場合には、必要に応じて専門機関と連携いたします。
- 環境調整・生活支援:スケジュール管理、タスクの分け方、注意がそれにくい工夫など、日常生活を整える支援をご提案します。
- 心理的サポート:ご希望に応じて、外部カウンセラーをご紹介することも可能です。
最後に
ADHDの診断は、単に病名をつけることが目的ではありません。
「今の困りごとにどう向き合うか」「より自分らしく生活するにはどうしたらいいか」を一緒に考えるためのスタートです。
診断を迷っている方も、確定を急ぐ必要はありません。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
LINEからのご予約は24時間受付中
まずはお気軽にご相談ください。スタッフが丁寧に対応いたします。

診療時間:平日20時まで|オンライン診療対応
対応疾患:うつ病/大人の発達障害/休職相談/診断書発行/中学生・高校生受診可/不登校相談
発達障害や不登校のお悩みにも、じっくりと向き合っています。
オンライン診療のご予約はこちら
全国どこからでも受診可能。スマホで簡単にご予約いただけます。