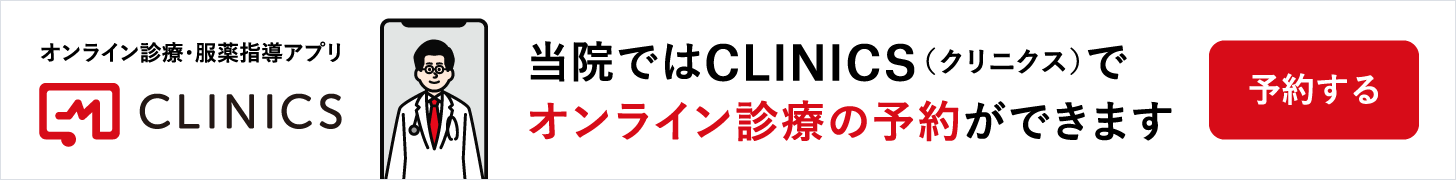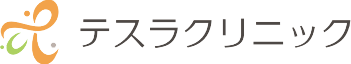2025年04月のブログ記事一覧
【中学受験・高校受験】合理的配慮の申請方法と注意点|現役医師がわかりやすく解説
2025.04.29
はじめに
「合理的配慮」という言葉を聞いたことはありますか?
受験の場面でも、障害のあるなしにかかわらず、すべての受験生が自分の力を正しく発揮できるように、環境を調整する配慮が求められます。
この記事では、合理的配慮の基本と、受験時における申請の流れや注意点について、わかりやすくまとめます。
合理的配慮とは?
合理的配慮とは、「障害のある人が、他の人と平等に機会を得られるようにするための支援」です。
日本では障害者差別解消法に基づき、2016年から国公立学校などで提供が義務化されています。
重要なのは、特別扱いをすることではなく、すべての人が公平に力を発揮できる環境を整えるための措置だということです。
本来、合理的配慮は障害の有無を問わず、「誰もが自分の力を発揮できるようにする社会的努力」として考えるべきものでもあります。
受験における合理的配慮の具体例
申請できる配慮内容は、受験生の特性に応じてさまざまです。たとえば:
- 試験時間の延長
(注意集中が困難な場合:例/ADHD〈注意欠如多動症〉など) - 別室受験
(集団環境にストレスを感じやすい場合:例/ASD〈自閉スペクトラム症〉など) - 休憩時間の追加
(強い不安やパニック発作が起こりやすい場合:例/パニック障害、不安障害など) - 読み上げ試験の実施
(読字が困難な場合:例/ディスレクシア〈読字障害〉など) - パソコン入力による解答
(手書きが極端に苦手な場合:例/発達性協調運動障害〈DCD〉、書字障害など)
※あくまで一例であり、実際には「診断名」ではなく、「本人が抱えている具体的な困難や支援ニーズ」をもとに検討されます。
配慮が必要かどうかは「一人ひとり異なる」
ここで大切なのは、
「同じ診断名でも、全員が同じ配慮を必要とするわけではない」
ということです。
例えば、ADHDと診断されている受験生でも、
- 試験中に集中が途切れやすい人
- 逆に試験環境では集中できる人
では、必要な配慮は異なります。
つまり、配慮の要否や内容は、
診断名だけではなく、本人の具体的な困難さや、受験環境における影響をもとに個別に判断される
という点を忘れてはいけません。
申請のタイミングと注意点
配慮申請のタイミングにも注意が必要です。
- 配慮申請は、通常の出願書類とは別に、専用の申請書類を提出する必要があります。
- 早い学校では、8月頃から配慮申請受付が開始される場合もあります。
- 出願締切よりも前に配慮申請の締切が設定されていることがあるため、要確認です。
▶ 必ず志望校の募集要項を細かく確認し、申請スケジュールを逃さないようにしましょう。
申請に必要な書類
一般的に求められる書類は次の通りです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 医師の診断書・意見書 | DSM-5やICD-10に準拠した診断名、障害特性、必要な配慮の根拠を記載 |
| 学校(在籍校)の意見書 | 日常生活や学習上の配慮状況、これまでの支援とその効果について記載 |
| 本人・保護者の申請理由書 | なぜ配慮が必要か、本人にとってどんな意味があるかを説明 |
※学校によってフォーマット指定がある場合もありますので、必ず個別に確認しましょう。
まとめ
受験は、受験生一人ひとりが持っている力を正当に評価されるべき場です。
合理的配慮の申請は、そのために必要な、大切な手続きのひとつです。
診断名の有無にかかわらず、本人が抱える具体的な困難に応じた支援を整えること。
そして、必要な配慮を早めに準備し、スムーズな受験当日を迎えること。
この両方を大切にして、ぜひ未来への一歩を踏み出してください。
【あとがき】
合理的配慮を申請することは、決して「甘え」ではありません。
合理的配慮とは、特別な扱いを求めるものではなく、誰もが公平に力を発揮できる環境を整えるための社会的な努力です。
法制度上は障害のある方への義務として位置づけられていますが、
実際には、すべての人にとって大切な考え方でもあります。
どうか、必要な支援を受け取り、あなたらしい未来を切り拓いてください。
TMS治療の費用対効果:うつ病治療、"早く治す"という選択肢
2025.04.15
うつ病は「時間をかけて治すもの」と思われがちですが、本当にそれがベストな選択でしょうか?
当院・テスラクリニックでは、**TMS治療(経頭蓋磁気刺激療法)を16回コース220,000円(税込)**でご提供しています。
この金額を聞いて、「高い」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも、それは「費用」だけを見たときの話です。
今日は、「費用対効果」という視点から、TMSの価値を一緒に考えてみたいと思います。
傷病手当とTMS治療、どちらが“安い”?
うつ病で働けず、傷病手当を受給しながら療養されている方は少なくありません。例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 月収:25万円の会社員
- 傷病手当金:およそ月額18〜20万円程度(額面の約2/3)
1ヶ月あたり18万円受け取りながら療養していたとしても、それはあくまで「収入が下がった状態」での生活です。
加えて、病気が長引けば長引くほど、復職のハードルも心理的負担も大きくなるのが現実。
一方、TMS治療では、およそ3〜4週間で16回~32回のTMSセッションを集中施行し、うつ状態の改善を早期に図ることが可能です。
副作用が少なく、治療抵抗性のうつ病や服薬での改善が難しい方にも適しています。
仮に2ヶ月で職場復帰できたとしたら?
治療なしで療養が6ヶ月かかった場合:
- 傷病手当収入:約108万円(18万円×6ヶ月)
- 給与との差額損失:約42万円
TMSで2ヶ月で復帰した場合:
- 傷病手当収入:約36万円(18万円×2ヶ月)
- TMS治療費:22万円
- 実質的な損失:約58万円 ⇒ 早期復帰により以後の月収が回復
つまり、復職が早まるだけで、給与差額がすぐにTMSの治療費を上回る可能性があるのです。
「未来に繋がる出費」か「長引くコスト」か
TMSは確かに保険適用外で、一見高額な自費診療です。
でも、それは「高額」ではなく「投資」ともいえるのではないでしょうか。
- 長引く不調による収入減
- 社会的孤立や将来への不安
- 家族や周囲への負担
これらを考慮すれば、「早く良くなること」が何よりのコストパフォーマンスだと、私たちは考えています。
最後に:あなたにとっての最善の選択を
TMSがすべての人に万能とは言いません。
でも、「薬が合わない」「副作用がつらい」「できれば早く社会復帰したい」と考えている方には、有力な選択肢のひとつです。
うつ病治療は“我慢比べ”ではありません。
「早く治す」という選択肢があることを、ぜひ知っていただけたらと思います。
📍テスラクリニックのTMS治療
- 16回コース:220,000円(税込)
- 1回あたり16分の短時間セッション
- 専門医による個別設計・伴走支援あり
まずはお気軽にご相談ください。早期回復への第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
ADHD治療が効かない…実は“気づかないうつ”だった? 脳波(QEEG)で見えた本当の原因
2025.04.15
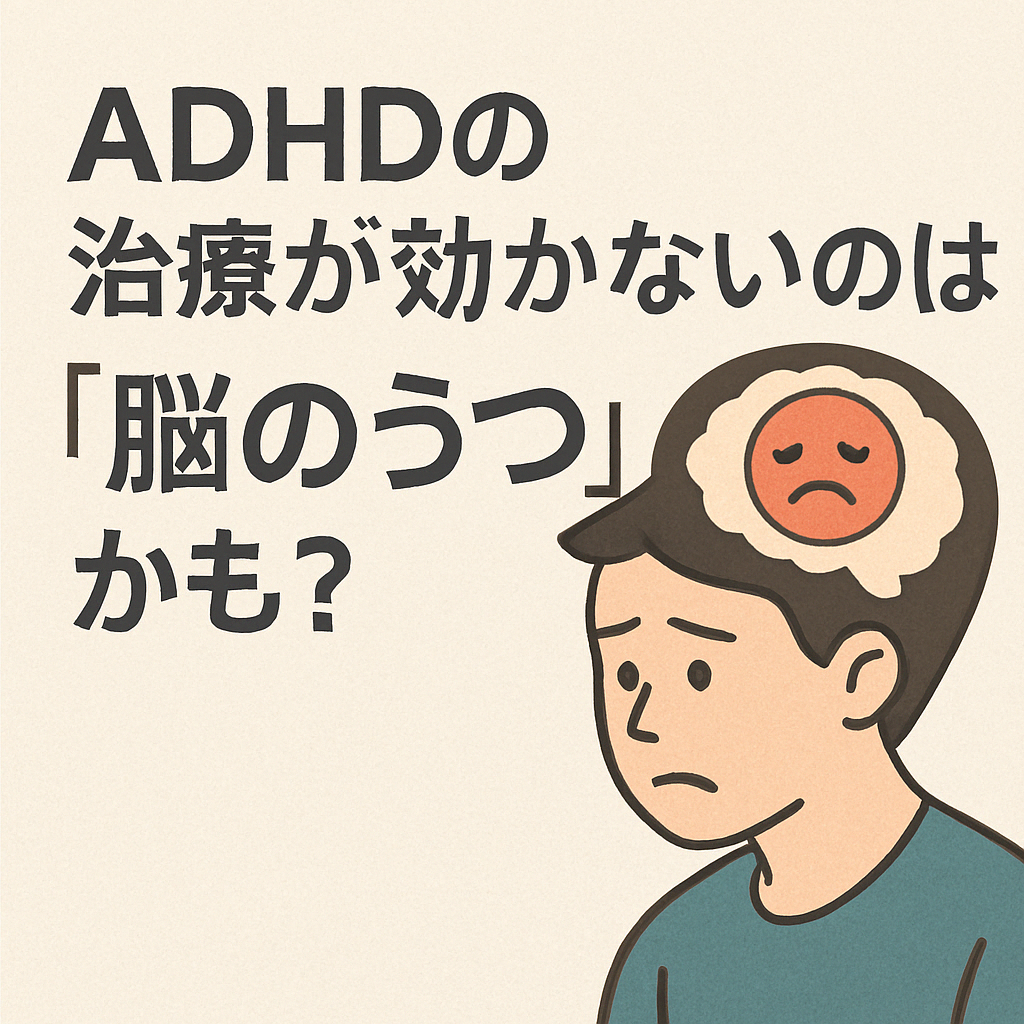
◆ はじめに
ADHDの診断を受け、薬も飲み、生活習慣も整えているのに、なぜか改善しない。
そんなとき、**本当の原因は“気づかないうつ状態”**かもしれません。
当院で行っている「QEEG(定量脳波)」検査によって、“こころ”ではなく“脳”の状態から原因が見えてくることがあります。
今回は、実際に「ADHDだけだと思っていた方」が、QEEGを通して別の側面に気づいたケースをご紹介します。
◆ ADHDと「うつ」は重なりやすい
ADHDと診断される方の中には、実は**気づかれていない“うつ状態”**が隠れているケースがあります。
たとえば、
- やる気が出ない
- ケアレスミスが多い
- 集中できない
…といった症状は、ADHDにも「うつ病」にも共通しています。
だからこそ「ADHDと思っていたら、実はうつだった」というケースも少なくありません。
◆ 自覚のない“うつ”もある
ある患者さんの話です。
ずっと「自分はADHDだからうまくいかない」と悩んでいましたが、うつ症状の自覚はほぼなし。
問診票(CES-D)でもスコアは低く、「私はうつじゃないと思います」と本人もはっきり言っていました。
ですが、脳波(QEEG)を取ってみると…
前頭葉を中心に、典型的なdepressionパターンが強く現れていたのです。
◆ QEEG(定量脳波)の可能性
QEEGとは、脳の活動パターンを定量的に見る検査です。
特定の脳部位が過活動になっていたり、逆に活動が低下している様子がわかります。
この方の場合は、
- 注意のネットワークに異常あり
- 同時に、うつに関連する部位での機能低下あり
つまり、「ADHDの顔をした“脳のうつ”」だったわけです。
こうした状態では、従来のADHD治療だけでは改善が難しいこともあります。
◆ 治療方針をどう変える?
QEEGの結果をもとに、治療方針を見直しました。
- ADHD薬物療法を見直し
- セロトニン系の調整と、脳機能を直接整えるTMS治療を検討
その結果、生活の安定度が高まり、患者さん自身も「頭の中がクリアになった」と実感されていました。
◆ まとめ:客観的指標を用いて「脳の状態」を再評価してみる
「うつだと思っていたらADHDだった」
「ADHDだと思っていたら“脳のうつ”だった」
心の問題は、ひとつのラベルでは説明できないことも多いです。
QEEGは、そんな見えない部分に光を当てるツールとして、私たちの診療にとても役立っています。
◆ ご相談ください
✔ ADHD治療をしているが効果を感じづらい
✔ 何が原因なのか、自分でもよくわからない
✔ 脳波での可視化に興味がある
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
脳の声を聴いて、より納得のいく治療を一緒に考えていきましょう。
TMS治療を考える前に読む ADHDとうつ・不安の話
2025.04.15
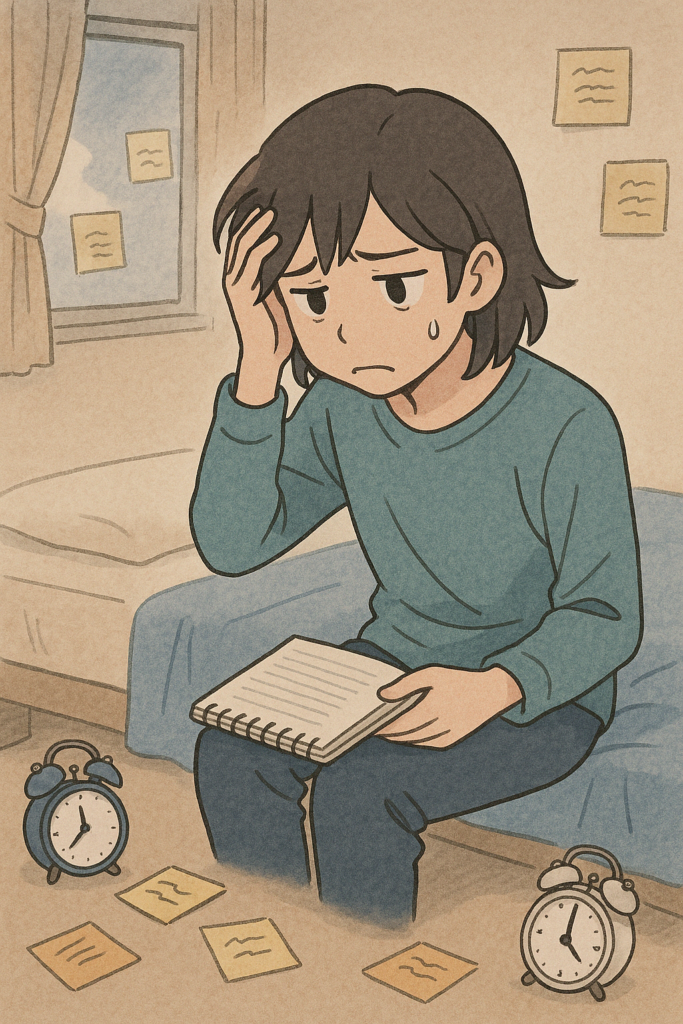
ADHDの診断を受けた方の中には、
「集中できないのは昔からだけど、最近は気分が落ち込みやすい」
「些細なことで不安が止まらず、眠れない」
といった “二次的な不調” を感じている方も少なくありません。
こうしたケースでは、ADHDそのものよりも、**「うつ」や「不安障害」**といった、いわゆる二次障害への対処が、生活の質を上げる鍵になります。
ADHDの“生きづらさ”が心の調子に影響する
ADHD(注意欠如・多動症)は、生まれ持った神経発達特性です。
苦手なことが人より多く、ミスを責められたり、努力が空回りしてしまう日々が続くと、
「自分はダメだ」「どうせうまくいかない」といった考えが積み重なってしまいます。
こうして生まれる 慢性的な自己否定感や緊張状態 が、
うつ状態や不安障害に繋がることは少なくありません。
「ADHDの薬が効かない」=TMSの出番?ではない
「ストラテラ(アトモキセチン)やインチュニブを飲んでも気分が晴れない」
「コンサータで集中できるようになっても、気持ちが重いまま」
こんな訴えを聞くこともあります。
ですが、ここで**「ADHDの薬が効かない=TMSに切り替えよう」**と判断するのは、まだ早いかもしれません。
多くの場合、薬が効かないわけではなく、
今、治療すべき“主な症状”がADHDではなく、うつや不安のほうにあるのです。
二次障害を見逃さないことが、治療の近道になる
TMS(経頭蓋磁気刺激療法)は、たしかに薬が効きづらい・副作用が出やすい方にとっての選択肢になります。
しかしその前に、
- 睡眠の質はどうか
- 思考のクセ(過剰な自己批判や未来への不安)はどうか
- 環境調整(働き方・人間関係など)がうまくいっているか
を丁寧に振り返ることで、薬物療法や心理療法のみで大きく改善するケースも多々あります。
TMSを使うかどうかの判断も、そういったアセスメントの先にあるべきなのです。
だからこそ、当院では「TMSありき」ではなく「全体の流れの中でTMSを使う」
当院でも、ADHDの方にTMS治療をご提案するケースはあります。
ただしそれは、「ADHDだからTMSをする」わけではありません。
うつや不安が強く、薬では十分な効果が得られず、
今この方の生活や心にとってTMSが本当にフィットしていると判断したときにのみ、ご案内しています。
最後に:自分の“今”を正しく知ることから始めよう
TMSは、心の回復を助ける大切なツールのひとつです。
でも、それを使うタイミングと、目的を見誤ってしまうと、
「良くならなかった」という残念な結果になりかねません。
「ADHDだけじゃなくて、最近気分も落ちてる気がする」
「TMSって気になるけど、私には合ってるのかな?」
そう思ったら、まずは今の状態を整理するところから一緒に始めましょう。
診断や治療法の選択は、ひとりで決めるものではなく、私たち医療者と一緒に考えていくものです。
📍 当院ではADHD・うつ・不安に関するご相談を受け付けています
丁寧なヒアリングと状態把握から、必要であればTMSのご提案も行っています。
うつ病治療に「伴走者(ピアサポート・家族・支援者)」は必要?研究が示す支えあいの力
2025.04.14
ADHDの診断ってどうするの?実際の流れを解説します
2025.04.07
「もしかしてADHDかもしれない」
「集中できず、ミスが多いことがずっと気になっている」
「子どものことで学校から指摘を受けた」
そんな悩みをきっかけに、当院には日々多くのご相談が寄せられています。
今回は、「ADHDの診断って実際にどう進めるの?」というご質問にお答えし、当院での基本的な流れをご紹介します。
① 予約と問診票の記入
当院では、初診前にオンラインで問診票をご記入いただいています。
問診票では、これまでの生活や現在の困りごと、過去の診断歴などをお伺いします。これにより、初診時からより具体的なご相談が可能になります。
② 初診(医師による診察)
初診では、今のお困りごとや生活の状況、これまでの経過などを丁寧にお聞きします。
特に以下のような点を確認します:
- 幼少期から現在までの行動傾向
- 忘れ物や遅刻、ケアレスミスの頻度
- 周囲からの指摘や対人関係の困難
- 学校・職場での適応の様子
必要に応じて、家族や関係者からの情報、通知表、既往歴なども参考にさせていただきます。
③ スクリーニング検査の実施
ADHDの診断にあたっては、DSM-5という診断基準に基づいて評価を行いますが、補助的に以下のような質問票・検査も使用しています:
- ASRS(Adult ADHD Self-Report Scale):成人のADHD傾向を評価する質問票
- AQ(Autism-Spectrum Quotient):ADHDと重なりやすい自閉スペクトラム傾向を評価
- WAIS / WISC:必要に応じて、認知特性を確認するための知能検査を実施することもあります(実施は主に2回目以降)
検査の有無や内容は、医師と相談しながら個別に決定します。
④ 診断と方針のご説明(暫定診断について)
ADHDの診断は、問診・検査・情報の総合判断で行いますが、初診時点では情報が不十分なことも多いため、当院では**「ADHDの可能性が高い(=暫定診断)」という形で様子を見ながら判断を進める場合があります**。
焦らず慎重に、「今の困りごとにどう対応できるか?」を一緒に考えることを大切にしています。必要に応じて、診断の精度を高めるために追加の情報提供や診察をお願いすることもあります。
⑤ 支援・治療の選択肢
診断の結果に応じて、以下のような方法を検討します:
- 薬物療法:症状や生活背景に応じて検討します。当院で対応が難しい場合には、必要に応じて専門機関と連携いたします。
- 環境調整・生活支援:スケジュール管理、タスクの分け方、注意がそれにくい工夫など、日常生活を整える支援をご提案します。
- 心理的サポート:ご希望に応じて、外部カウンセラーをご紹介することも可能です。
最後に
ADHDの診断は、単に病名をつけることが目的ではありません。
「今の困りごとにどう向き合うか」「より自分らしく生活するにはどうしたらいいか」を一緒に考えるためのスタートです。
診断を迷っている方も、確定を急ぐ必要はありません。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
LINEからのご予約は24時間受付中
まずはお気軽にご相談ください。スタッフが丁寧に対応いたします。

診療時間:平日20時まで|オンライン診療対応
対応疾患:うつ病/大人の発達障害/休職相談/診断書発行/中学生・高校生受診可/不登校相談
発達障害や不登校のお悩みにも、じっくりと向き合っています。
オンライン診療のご予約はこちら
全国どこからでも受診可能。スマホで簡単にご予約いただけます。
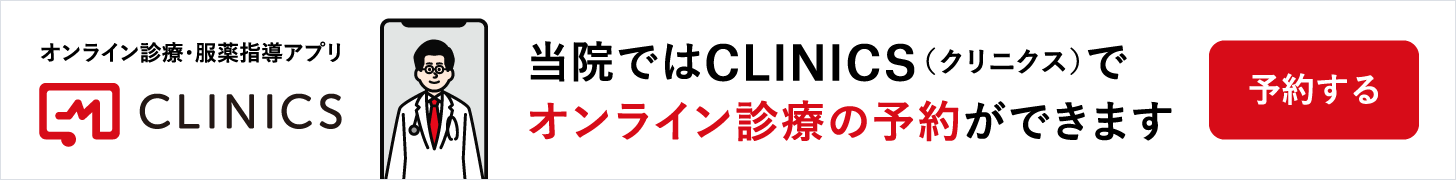
✅大人のADHDセルフチェックリスト(簡易版)
2025.04.07
大人のADHD(注意欠如・多動症)の傾向をセルフチェックできる簡易リストをご紹介。
気になる方は早めの相談をおすすめします。
以下の質問に、過去6か月の自分の様子を思い浮かべながらお答えください。
あてはまる項目の数を数えてみましょう。
🔹不注意に関するチェック(1〜9)
- 細かいことを見落としたり、ケアレスミスが多い
- 課題や仕事で注意を持続するのが難しい
- 話を聞いている時に注意がそれやすい
- 指示に従うのが苦手で、やり残しが多い
- 作業を順序立てて行うのが苦手
- 長期の課題や仕事を避けたり、後回しにしがち
- 必要な物をよくなくす(例:鍵、財布、スマホなど)
- 外部の刺激(音や人の動き)で気が散りやすい
- 日々の予定や約束を忘れがち
🔹多動性・衝動性に関するチェック(10〜18)
- 落ち着いて座っていられないことが多い
- 手足を動かしてしまう、ソワソワする
- 静かに過ごすのが苦手
- 話しすぎてしまう
- 質問が終わる前に答えてしまう
- 順番を待つのが苦手
- 他人の会話や行動に割り込んでしまう
- 物事にすぐに飽きてしまう
- 衝動的な買い物や行動をして後悔することがある
📝チェックの目安
- 各項目に「5つ以上」あてはまる場合は、ADHDの傾向があるかもしれません。
- 日常生活や仕事に支障があると感じる方は、一度専門の医療機関で相談されることをおすすめします。
💡ご注意ください
このチェックリストはあくまで簡易的な自己評価ツールであり、診断を行うものではありません。正確な診断には、医療機関での専門的な評価が必要です。
📩当院ではADHDに関するご相談を受け付けています
「これってADHDかも?」と感じたら、まずは一度ご相談ください。
ご希望の方にはASRSなどの正式なチェックシートもご案内しています。
LINEからのご予約は24時間受付中
まずはお気軽にご相談ください。スタッフが丁寧に対応いたします。

診療時間:平日20時まで|オンライン診療対応
対応疾患:うつ病/大人の発達障害/休職相談/診断書発行/中学生・高校生受診可/不登校相談
発達障害や不登校のお悩みにも、じっくりと向き合っています。
オンライン診療のご予約はこちら
全国どこからでも受診可能。スマホで簡単にご予約いただけます。
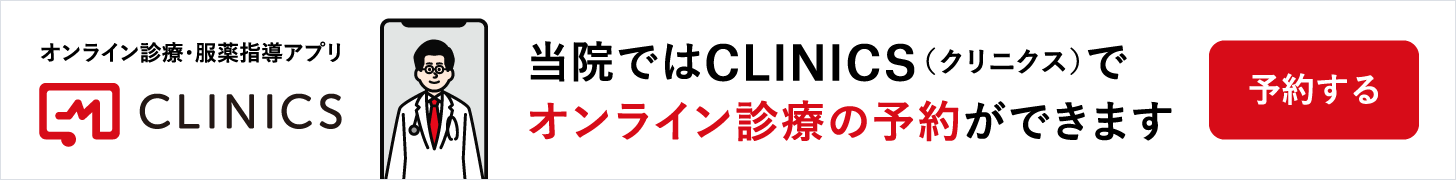
ADHDと仕事のミス:なぜ繰り返す?どう対策する?
2025.04.06
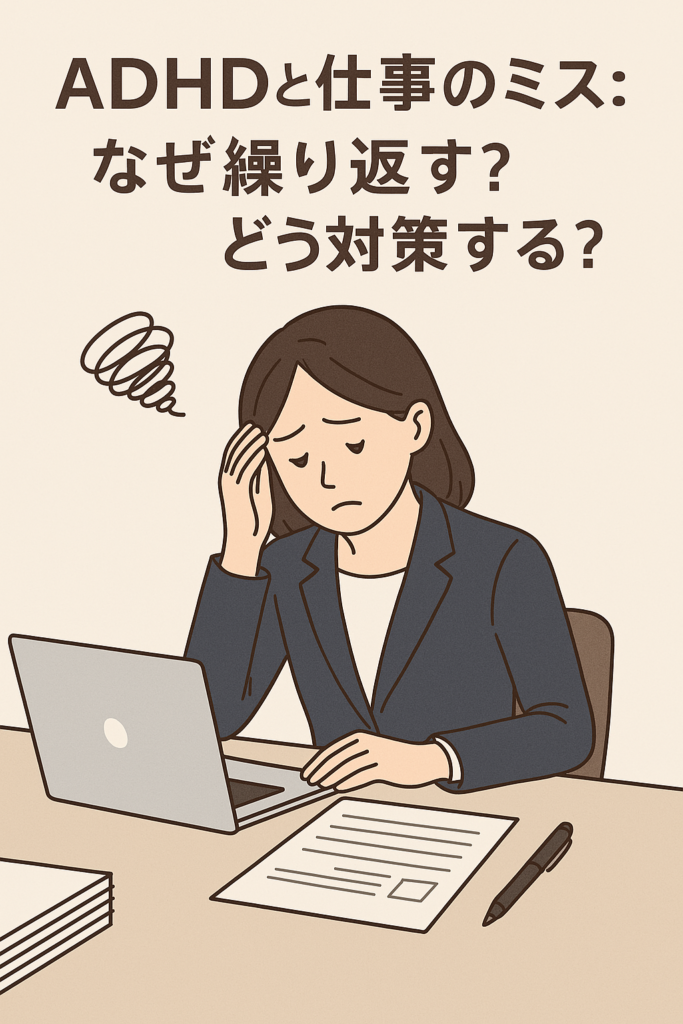
この記事の要約: 職場で同じミスを繰り返してしまうタイプのADHD患者さん。原因と実践的な対策について医師の視点で解説します。自分を責める前に、できる工夫を知りましょう。
ADHDと仕事のミス:なぜ繰り返す?どう対策する?
「またやってしまった……」
書類の提出忘れ、会議の時間を勘違い、同じ指摘を何度もされてしまう——
職場でのミスが続くと、自信を失ってしまいますよね。
今回は、ADHD(注意欠如・多動症)と仕事のミスの関係について、「なぜ同じようなミスを繰り返してしまうのか」、そして「どうすればそれを減らしていけるのか」について、精神科医の視点からわかりやすく解説します。
なぜミスを繰り返してしまうのか?
ADHDの方が仕事でミスを繰り返しやすいのは、性格の問題ではありません。脳の「注意」「記憶」「実行機能」に関わる特性が影響しています。
主な要因は以下の3つです:
- 注意が持続しにくい
他の刺激に気を取られやすく、書類の誤字脱字、抜け漏れが発生しやすい。 - 短期記憶(ワーキングメモリー)が不安定
「あとでやろう」「覚えてるつもり」が抜け落ちやすい。 - タスクの優先順位づけが苦手
締切ギリギリになることが多く、焦りからさらにミスが増える。
自分を責めすぎないで
「なんでこんな簡単なことができないんだろう…」と自分を責めてしまう方も多いですが、それはあなたの能力や努力の問題ではありません。
ADHDの特性に合った「仕組み」や「環境」が整っていないだけなのです。逆に言えば、環境や工夫次第で、ミスを減らすことは十分に可能です。
ADHDの方向け:ミスを減らすための実践的な対策
1. すべて「見える化」する
- TODOリストは「スマホ」より「紙+目の前」が効果的。
2. タスクを「1つずつ」に分ける
- 「資料作成」ではなく「構成→図探し→文章」と細分化。
3. ミスの傾向を記録する
- 記録→振り返りでパターンを見つけ、事前に予防。
4. 周囲に相談・共有する
- 「忘れっぽいのでリマインドしてほしい」と伝えるのも自己管理。
5. 医療の力を借りることも選択肢のひとつ
- 神経発達症治療薬の力を借りることで、注意力や集中力が安定することがあります。
最後に
ADHDのある方が職場でうまくいかないとき、問題は「あなた自身」ではなく、「特性に合っていないやり方や環境」にあることが多いのです。
ひとりで抱えず、信頼できる人や医療機関に相談することが、ミスの連鎖から抜け出す第一歩になるかもしれません。
▼関連リンク
よくある質問(FAQ)
Q. ADHDと診断されていなくても読んでいいですか?
A. もちろんです。「もしかして…?」と感じる方にも役立つ内容になっています。
Q. 薬を使わないと改善できませんか?
A. 環境調整や行動の工夫だけでも、日常生活は大きく改善する可能性があります。ただし、薬の力を借りた方が圧倒的に楽なケースが多いです。
LINEからのご予約は24時間受付中
まずはお気軽にご相談ください。スタッフが丁寧に対応いたします。

診療時間:平日20時まで|オンライン診療対応
対応疾患:うつ病/大人の発達障害/休職相談/診断書発行/中学生・高校生受診可/不登校相談
発達障害や不登校のお悩みにも、じっくりと向き合っています。
オンライン診療のご予約はこちら
全国どこからでも受診可能。スマホで簡単にご予約いただけます。
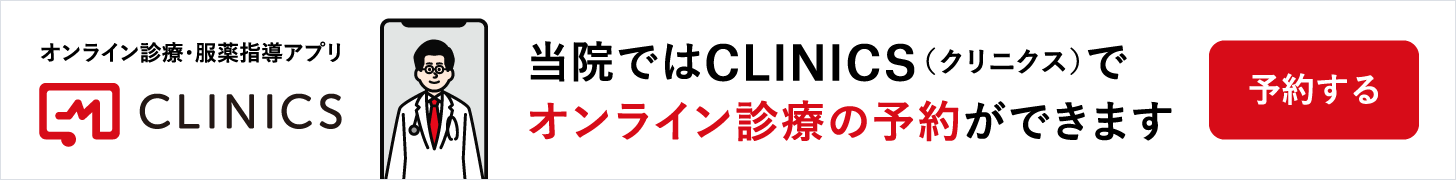
「バレる嘘」をついてしまう——ADHDの大人に見られる“とっさのごまかし”とその理由【大人の発達障害】
2025.04.06
この記事の要約: ADHDの大人が嘘をついてしまうのは、衝動性や不安が関係しています。この記事ではその理由と対処法を解説します。
はじめに:なぜ「そんな嘘ついたの?」が起きるのか?
- 「なんでそんな嘘ついたの?」
- 「隠すほどのことじゃないのに、なんでごまかすの?」
ADHDの診断を受けた大人の方と話していると、こうした“その場しのぎの嘘”について悩んでいる方がとても多くいます。
しかも、ほとんどの場合、その嘘はすぐにバレてしまう——。
この行動、実はADHDの特性と深く関わっており、意志の弱さや誠実さの問題ではありません。
今回はその背景と、実生活でできる対処法をお伝えします。
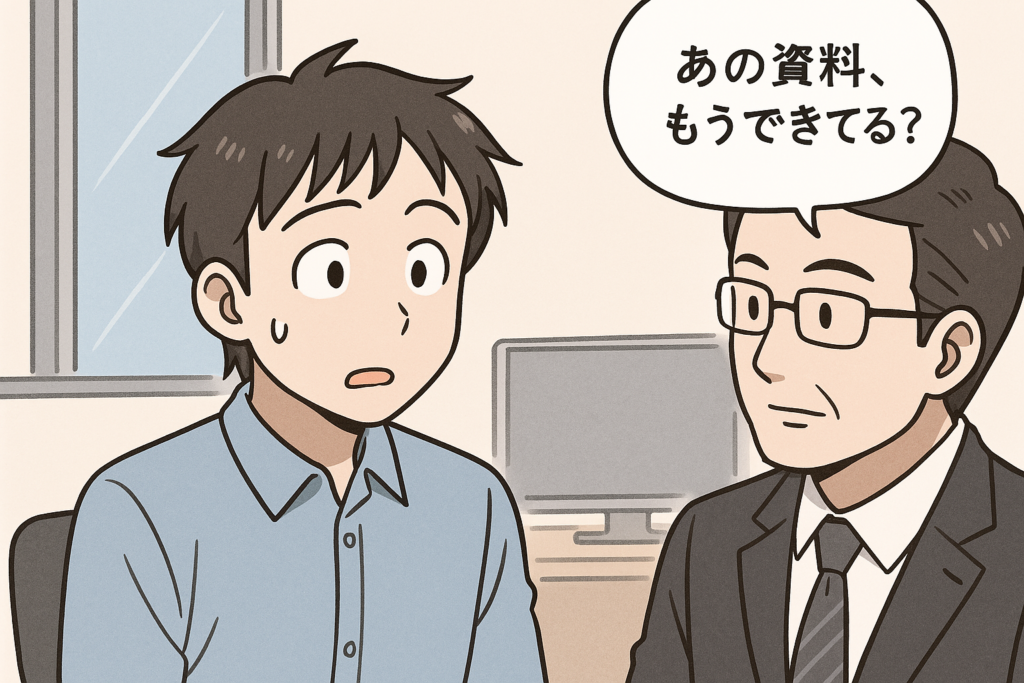
ADHDの大人が「嘘をついてしまう」3つの理由
① 衝動性と焦りによる“口が先に出る”反応
ADHDの特徴のひとつに、「衝動性」があります。
「やばい、まずい!」と焦ったとき、深く考える前に口が先に動いてしまうことがあります。
→その結果、うまく話を組み立てる時間がなく、「適当なことを言ってしまった」とあとから自己嫌悪に。
② ワーキングメモリの弱さによる混乱
ADHDの方は、会話中に「何を聞かれたのか」「どう答えるべきか」などの情報を整理するのが苦手です。
とっさの受け答えに混乱し、「場をつなぐために嘘っぽいことを言ってしまう」ことがあります。
→あとから「言ってることが矛盾してる」と気づき、自分でも恥ずかしくなる場面も。
③ 自己肯定感の低さと過去の経験
「また怒られる」「また失望される」
そんな経験が重なると、正直に話す=リスクという認知が根付いてしまいます。
→すると無意識に“ごまかし”や“言い逃れ”を選びやすくなります。
「嘘をつかずにすむ」ようになるための実践ステップ
✅ ステップ①:正直に話してうまくいった体験を振り返る
- 「謝ったら、ちゃんと理解してもらえた」
- 「正直に報告したら、むしろ信頼された」
そんな経験、実は過去にありませんでしたか?
**嘘をつかなかった結果の“成功体験”**を思い出すことは、嘘を減らす第一歩になります。
✅ ステップ②:「嘘をつきたくなる瞬間」を把握する
- 遅刻したとき
- 締め切りを忘れていたとき
- ついスマホを見ていたとき
こういった自分の“トリガー”を理解することで、嘘のパターンに気づきやすくなります。
✅ ステップ③:安心して話せる関係・環境を作る
「本当のことを言っても大丈夫」と感じられる環境があれば、防衛的な嘘をつかずにすみます。
職場や家庭で自分の特性を共有できる関係性を、少しずつでも作っていきましょう。
関連記事(内部リンク)
まとめ:嘘を責めるより、背景に目を向けてみよう
ADHDの大人が「バレる嘘をついてしまう」のは、ズルさではなく、不安や衝動への反応です。
そしてその多くは、本人自身もあとから「やらかした…」と後悔しています。
嘘を責めるのではなく、「なぜそうしたのか?」に目を向けることで、改善の糸口は必ず見えてきます。
そして何より大切なのは、「素直に話してもいいんだ」と思えるような安心できる関係性。
それは、自分で作ることも、誰かと一緒に育てることもできるのです。
ご相談はいつでもどうぞ。
「嘘をやめたい」「信頼を取り戻したい」と思っているあなたの力になれたらと思います。
💡補足:このような傾向のある方へ
当院では、大人の発達障害・ADHDに関する心理的支援や生活アドバイスも行っています。
ご相談をご希望の方は、公式LINEから予約・事前問診が可能です。お気軽にご利用ください。
LINEからのご予約は24時間受付中
まずはお気軽にご相談ください。スタッフが丁寧に対応いたします。

診療時間:平日20時まで|オンライン診療対応
対応疾患:うつ病/大人の発達障害/休職相談/診断書発行/中学生・高校生受診可/不登校相談
発達障害や不登校のお悩みにも、じっくりと向き合っています。
オンライン診療のご予約はこちら
全国どこからでも受診可能。スマホで簡単にご予約いただけます。