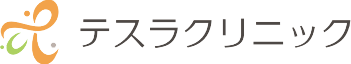2025年07月のブログ記事一覧
適応障害?それともうつ病?病院を受診するのはいつがいい?
2025.07.28
はじめに:誰にでも起こりうる「心の不調」
「最近、仕事がつらい」「涙が出る」「朝起きられない」「でも、これって“病気”なのかな?」
そんな疑問を持ってこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
心の不調は誰にでも起こりえます。
しかし、「これって適応障害?うつ病?それともただのストレス?」と迷ったとき、受診のタイミングを逃さないことがとても大切です。
適応障害とうつ病の違いとは?
| 項目 | 適応障害 | うつ病 |
|---|---|---|
| 原因 | 明確なストレス因(例:職場の異動、家庭内トラブルなど) | 原因が明確でないことも多い |
| 症状 | 抑うつ、不安、イライラ、不眠などがストレス状況に反応して出現 | 気分の落ち込み、意欲低下、興味喪失、自責感、希死念慮などが持続的にみられる |
| 経過 | 原因から離れると改善することが多い | 時間が経っても自然回復しにくく、長期化しやすい |
| 重症度 | 軽度〜中等度 | 中等度〜重度 |
※DSM-5を基に整理
どんなときに受診したらいい?
受診を検討すべき目安を以下に整理します:
✅ 2週間以上、不調が続いている
- 気分の落ち込み、食欲低下、眠れない、仕事に行けない etc.
✅ 日常生活や仕事に支障が出てきた
- 遅刻・欠勤が増えている
- ミスが多く、集中できない
- 人と会うのがおっくうになってきた
✅ 身体にも影響が出ている
- 胃痛や頭痛が続く
- 何度も風邪を引くようになった
- 朝が特につらくて起きられない
✅ 「もう限界かもしれない」と感じる瞬間がある
- 「自分がいない方がいい」と思ってしまう
- SNSを見ていて涙が出る
- 怒りや不安がコントロールできない
よくある相談:「受診するほどじゃないと思ってた」
実際、初診時によく聞かれる言葉があります。
「もっと早く来ればよかった」
「自分では“甘え”だと思ってた」
「休むことに罪悪感があって……」
こうした思い込みが回復を遅らせてしまうこともあります。
メンタルの不調は早めに相談すればするほど軽症で済みます。
病気かどうかを判断するのは医師に任せて、気になる時点で受診してよいと思われます。
適応障害から「うつ病」へ──進行してしまうケースも
適応障害は、ストレス源(職場・家庭など)からの影響によって一時的に心身のバランスが崩れる状態です。
しかし、放置したり無理を続けたりすると、次第にストレス耐性が低下し、うつ病へ移行することがあります。
【進行例】
- 最初は「会社の上司との関係がつらい」という不安や焦燥感だった
- 我慢し続けるうちに食欲がなくなり、寝ても疲れが取れないように
- 次第に「自分がダメだからだ」「消えてしまいたい」という気持ちに
- 通院したときには、すでに中等度以上のうつ病と診断された
このように、「環境ストレス」が発端でも、長期化・重症化して「病気の自律性」が強くなると、単なる適応障害では済まなくなってしまいます。
「休む」ことが、なぜこんなに難しいのか?
多くの方が、医師に「一度休みましょう」と勧められたとき、こう答えます:
「迷惑をかけたくない」
「休むなんて甘えているみたいで……」
「みんな我慢してるのに自分だけ休むのはダメだと思った」
しかし、こうした思い込みこそが回復を遅らせてしまいます。
休むとは「逃げ」ではなく、回復に必要な“治療のひとつ”です。
例えば骨折したらギプスで固定し、安静にするように、こころの疲労にも「休息という処方」が必要です。
治療・療養のポイント
- 休職や休学は「自己責任」ではなく「治療の一環」
- 医師の診断書があれば制度的にも休むことが認められることが多い
- 精神保健の制度(傷病手当、自立支援医療など)で経済的なサポートも可能
まとめ:悩んだら、まずは相談を
- 適応障害とうつ病は“重なって”現れることもあります
- 病気かどうかを「自己診断」しすぎないでください
- 心や体に不調が出たら、それはすでにサインです
「病院に行ってもいいのか?」と迷ったら、それはもう行っていいサインです。
ご相談はお気軽に
当院では初診の方でも安心してご相談いただけるよう、WEB問診やLINEでの事前相談もご用意しています。
気になる症状がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
減酒の薬、セリンクロ──やめなくていいお酒の治療の話
2025.07.01
「お酒をやめるのは無理。でも、減らしたい」
そんな声を多く耳にします。
仕事のストレス、人付き合い、孤独感──
飲酒の背景には、それぞれの人生があります。
けれど、飲みすぎによって健康を損ねたり、家庭や仕事に影響が出始めたりすると、「そろそろ向き合わなければ」と感じる方も少なくありません。
完全にやめるのは難しいけれど、「少しずつでも減らせたら」。
そのような方に対して、医学的にアプローチできる選択肢のひとつが**セリンクロ(一般名:ナルメフェン)**です。
セリンクロとは?──“飲酒前に飲む”減酒の薬
セリンクロは、アルコール依存症の方を対象とした治療薬です。
従来の治療薬とは異なり、「断酒」ではなく「減酒」を目的としています。
- 服用タイミング:お酒を飲む可能性のある日の、飲酒の1〜2時間前に1錠
- 作用機序:脳の報酬系に働きかけ、飲酒による快感を和らげる
- 特徴:毎日飲まなくてもよい“必要時服用型”
つまり、「今日は飲んでしまいそうだな」と思う日だけ服用する薬です。
完全にやめるのが難しい方でも、少しずつ飲酒の頻度や量をコントロールする手助けになります。
とはいえ──治療の第一選択は「断酒」です
ここで大切なことをお伝えします。
セリンクロは確かに画期的な薬ですが、**アルコール依存症の標準的な治療はあくまで「断酒」**です。
セリンクロは、どうしても断酒が難しい場合に、次善の策として「減酒から始めたい」という希望に寄り添う選択肢です。
したがって、対象となるのは医師が「アルコール依存症」と診断した方のみです。
単なる“飲みすぎ”や“気になる程度”では処方の対象にはなりません。
「飲んだ量」を記録してみませんか?──減酒にっきアプリの活用
減酒治療をサポートするツールとして、**大塚製薬が提供している無料アプリ『減酒にっき』**があります。
- 飲酒日・飲酒量の記録
- 飲まなかった日には「クローバー」、適量の日には「スマイル」などの視覚的フィードバック
- 日記形式で気分や体調も記録可能
こうした自己観察の習慣は、セリンクロの効果をより実感しやすくするだけでなく、自分自身の変化に気づく大きな手がかりになります。
※アプリの使用だけで治療が完結するわけではなく、医師の診察と併用して用いることが推奨されています。
最後に──「お酒をやめるか、やめないか」はあなたが決めていい
減酒治療の目的は、「依存に支配されない人生を取り戻すこと」です。
そのための方法が、断酒であっても、減酒であっても、「自分で選ぶ」ことが何より大切です。
当院では、アルコールとの付き合い方を見直したいと考えている方のご相談をお受けしています。
ひとりで抱え込まず、まずは話してみませんか?
※ご注意
- セリンクロは、医師の診断と処方が必要な医療用医薬品です。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定の治療を推奨するものではありません。
- 治療の可否や適応については、必ず医療機関でご相談ください。