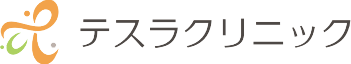TMS治療を考える前に読む ADHDとうつ・不安の話
2025.04.15
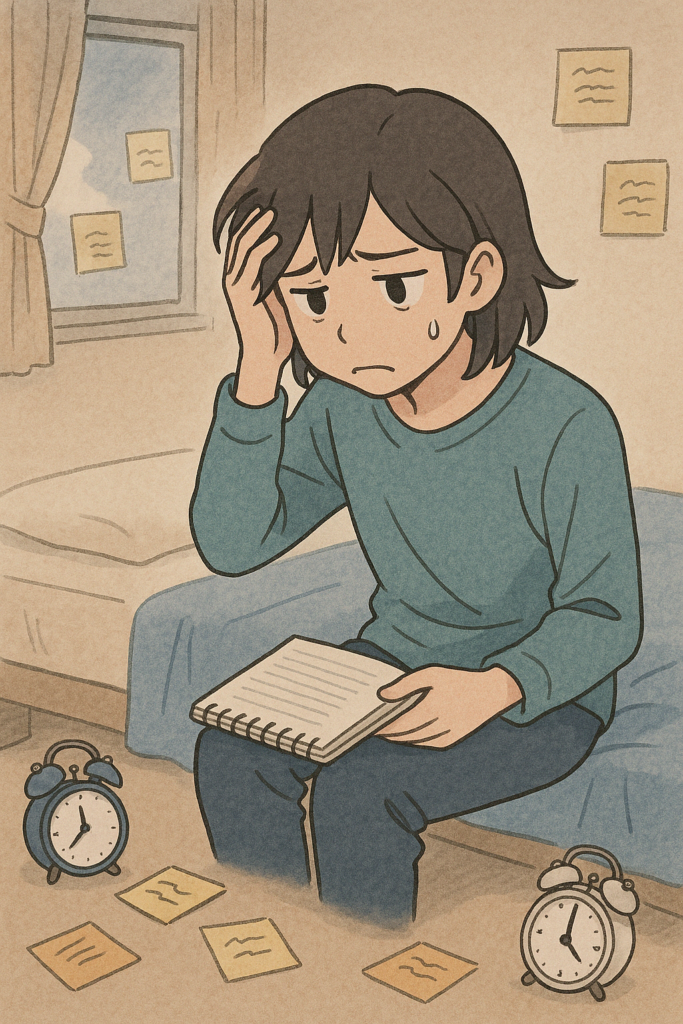
ADHDの診断を受けた方の中には、
「集中できないのは昔からだけど、最近は気分が落ち込みやすい」
「些細なことで不安が止まらず、眠れない」
といった “二次的な不調” を感じている方も少なくありません。
こうしたケースでは、ADHDそのものよりも、**「うつ」や「不安障害」**といった、いわゆる二次障害への対処が、生活の質を上げる鍵になります。
ADHDの“生きづらさ”が心の調子に影響する
ADHD(注意欠如・多動症)は、生まれ持った神経発達特性です。
苦手なことが人より多く、ミスを責められたり、努力が空回りしてしまう日々が続くと、
「自分はダメだ」「どうせうまくいかない」といった考えが積み重なってしまいます。
こうして生まれる 慢性的な自己否定感や緊張状態 が、
うつ状態や不安障害に繋がることは少なくありません。
「ADHDの薬が効かない」=TMSの出番?ではない
「ストラテラ(アトモキセチン)やインチュニブを飲んでも気分が晴れない」
「コンサータで集中できるようになっても、気持ちが重いまま」
こんな訴えを聞くこともあります。
ですが、ここで**「ADHDの薬が効かない=TMSに切り替えよう」**と判断するのは、まだ早いかもしれません。
多くの場合、薬が効かないわけではなく、
今、治療すべき“主な症状”がADHDではなく、うつや不安のほうにあるのです。
二次障害を見逃さないことが、治療の近道になる
TMS(経頭蓋磁気刺激療法)は、たしかに薬が効きづらい・副作用が出やすい方にとっての選択肢になります。
しかしその前に、
- 睡眠の質はどうか
- 思考のクセ(過剰な自己批判や未来への不安)はどうか
- 環境調整(働き方・人間関係など)がうまくいっているか
を丁寧に振り返ることで、薬物療法や心理療法のみで大きく改善するケースも多々あります。
TMSを使うかどうかの判断も、そういったアセスメントの先にあるべきなのです。
だからこそ、当院では「TMSありき」ではなく「全体の流れの中でTMSを使う」
当院でも、ADHDの方にTMS治療をご提案するケースはあります。
ただしそれは、「ADHDだからTMSをする」わけではありません。
うつや不安が強く、薬では十分な効果が得られず、
今この方の生活や心にとってTMSが本当にフィットしていると判断したときにのみ、ご案内しています。
最後に:自分の“今”を正しく知ることから始めよう
TMSは、心の回復を助ける大切なツールのひとつです。
でも、それを使うタイミングと、目的を見誤ってしまうと、
「良くならなかった」という残念な結果になりかねません。
「ADHDだけじゃなくて、最近気分も落ちてる気がする」
「TMSって気になるけど、私には合ってるのかな?」
そう思ったら、まずは今の状態を整理するところから一緒に始めましょう。
診断や治療法の選択は、ひとりで決めるものではなく、私たち医療者と一緒に考えていくものです。
📍 当院ではADHD・うつ・不安に関するご相談を受け付けています
丁寧なヒアリングと状態把握から、必要であればTMSのご提案も行っています。