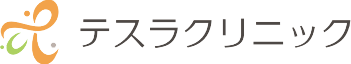発達障害の“診断基準外”の症状は、合理的配慮の対象になるのか?
2025.11.26
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)には、DSM-5という正式な診断基準があります。しかし実際の臨床現場では、診断基準に書かれていないのに、当事者の多くが共通して経験している現象 が少なくありません。
たとえば、
- APD(聴覚情報処理の困難:声は聞こえるが意味が届かない)
- DCD(協調運動の困難:靴ひもが結べない、ぶつかりやすい)
- 時間感覚のズレ(タイム・ブラインドネス)
- マルチタスク困難、フリーズ
- 刺激の選別が苦手(雑音で思考が停止する)
- 感情同定の難しさ(アレキシサイミア)
これらは診断基準には明記されていませんが、日常生活・学校・職場に大きな影響を与える“周辺症状” です。
では、こうした“診断基準外の特性”は 合理的配慮の対象になるのでしょうか?
結論からいえば、多くの場合、対象になります。
■ 合理的配慮は「診断名」ではなく「困りごと」で判断される
合理的配慮の実務では、
「医学的な診断項目を満たしているか」よりも
「生活や学業・業務に具体的な支障があるか」
が最も重要です。
実際、学校や企業が合理的配慮を検討するときの流れは次の通りです。
- 本人が困っている具体的な状況
- その困難が学習や業務にどう影響しているか
- どう調整すれば改善するか
この3つが揃っていれば、診断基準に載らない症状でも配慮の対象になる ことは珍しくありません。
■ APD・DCDはむしろ「配慮の必要性が高い」領域
● APD(聴覚情報処理の困難)
- 音声は聞こえるのに意味が入らない
- 複数人の会話になると処理できない
- 雑音が混ざると指示を理解できない
→ 席の調整、文字情報の併用、静かな環境の確保などの配慮が有効です。
● DCD(協調運動の困難)
- 手先の作業が極端に難しい
- 歩行中に人のかかとを踏みやすい
- 道具操作が遅れる
→ 作業時間の延長、安全な動線、道具の標準化などが役立ちます。
これらはDSM-5のASD/ADHD基準の“外側”ですが、生活機能への影響は非常に大きいため、配慮の対象となるケースが実際には多いのです。
■ 診断基準には載らないが、配慮が必要になりやすい特性
以下は、診断基準外であっても、合理的配慮として調整されることが多い“典型的な困難”です。
① 時間感覚のズレ(タイム・ブラインドネス)
- 5分後が想像できない
- 締切の実感がない
- 時間の流れが人と違う
→ タスクの細分化、スケジュール可視化が有効。
② 刺激の選別が苦手
- 雑音があると処理不能
- カフェやオープンスペースで集中できない
- 周囲の声や動きに意識を持っていかれる
→ 環境調整、席順配慮、ノイズ軽減が役立つ。
③ マルチタスク困難・フリーズ
- 作業と会話を同時にすると破綻する
- 切り替えの瞬間に固まる
- 頭が真っ白になり言葉が出ない
→ 作業環境の整理、単一タスク化で改善する場合が多い。
④ 感情の“名前がわからない”:アレキシサイミア
- 自分の状態を言語化できない
- ストレスが身体症状として先に出る
- 対話型の支援が難しいこともある
→ 記録・チャート・チェックリストで可視化すると支えやすい。
■ 合理的配慮として認められるかどうかの基準
以下のいずれかに当てはまれば、合理的配慮の検討対象となります。
- 困難が反復的で、生活機能の妨げになっている
- 本人の努力だけでは改善が難しい
- 認知・感覚の特性として説明がつく
- 学業・業務で不利益が生じている
- 第三者が見ても必要性が合理的に説明できる
つまり、“診断基準外だから対象にならない”ということはない のです。
■ まとめ
発達障害の周辺症状は、診断名以上に本人の生活を左右します。
合理的配慮は、本来こうした“現実の困りごと”を拾い上げる仕組みです。
- APD
- DCD
- タイム・ブラインドネス
- フリーズ
- 刺激の選別困難
- 感情の同定困難
これらはすべて、日常生活や学業・仕事に支障があれば、合理的配慮の対象になりうる領域 です。
診断名はあくまで枠組み。
その外側にも、多くの“生きづらさ”と“支援の必要性”があります。