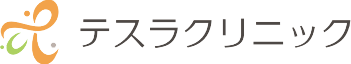「叱らない子育て」で家庭が不安定になる理由──社会的フィードバックと自我境界の発達
2025.11.17
「叱らない子育て」で狂ってしまった親子関係をたくさんみてきた。
とある精神科医の先生のツイートがバズっています。
否定語を使わない、子どもの気持ちを尊重する、親が怒らない──こうした姿勢自体は、たしかに子どもの安心感を育む上でとても大切です。
しかし臨床の現場では、“叱らない”“制止しない”“境界を示さない”というスタイルが続くことで、かえって家庭が不安定になっていくケースを数多く経験します。
それは親が悪いわけでも、子どもが悪いわけでもありません。
「社会的フィードバック」 と 「自我境界の発達」 という、人の成長に不可欠な仕組みが働かなくなるからです。
この構造を、少し丁寧に説明していきます。
1. 子どもは“外界とのやり取り”で世界を学ぶ
私たち大人は、
「これは危険なんだ」
「これは相手が嫌がるんだ」
「ここまでは許されるんだ」
という“外界のルール”を日常的なやり取りの中で自然に学んできました。
これを発達心理学では 社会的フィードバック(social feedback) と呼びます。
- 親の表情
- 声のトーン
- 止める・制止する
- 叱る・説明する
- 「それはダメ」「これはOK」という線引き
こうした反応を通じて、子どもは 「自分と他者は違う存在」 であり、
「他者にも独自の基準や感情がある」 ことを理解していきます。
これは 自我境界(self–other boundary) の発達そのものです。
2. “叱らない”が続くと、フィードバックが不足する
ところが、叱らない・制止しない・曖昧に終わらせる子育てが続くと、
子どもは「外界の反応」を手がかりにできなくなります。
例えば、
- 危険行動を止めてもらえない
- 他者が不快に感じても、そのサインが返ってこない
- 「良い・悪い」の境界がわからない
- 行動の可否が日によって変わる
こうした環境では、子どもは
“世界のルールが見えない”
という状態に置かれます。
世界の法則性がつかめないと、
子どもは自分の内部で“独自ルール”を作ってしまったり、
突然の変化に強い不安を感じやすくなります。
3. 境界が示されないと、子どもの心は不安定になる
自我境界は「他者との距離感」を学ぶための基盤です。
ところが境界が曖昧だと、次のようなことが起きます。
◆ 自分の気持ちと他者の気持ちが混ざる
自分の欲求が通らないとき、「拒絶された」と過剰に受け止めることがあります。
◆ 他者の基準が読み取れない
相手が何を嫌がるのか予測できず、対人不安が強まります。
◆ ルールが自分の中だけで完結してしまう
周囲との摩擦が増え、トラブルが起こりやすくなります。
境界が存在しない世界では、
子どもは「世界が突然変わるように感じる」ため、
家族内の怒り・不安・混乱も増えやすいのです。
4. 子どもが落ち着くのは“境界が設定されているとき”のことが多い
臨床でよく見かける印象的な現象があります。
「ダメな時はダメ」と明確に示した方が、子どもが落ち着く。
怒鳴る必要はありません。
理不尽に叱りつける必要もありません。
ただ、
- 危険な行動は止める
- 人を傷つける行動は制止する
- “家庭や学校のルール”を一貫して伝える
こうした “境界の明示”は、子どもにとって“世界の地図”になる のです。
5. では、どう叱ればよいのか?
叱る=怒鳴る ではありません。
子どもの発達に必要なのは 「情報としての叱り」 です。
- 何が危険なのか
- どこまでOKで、どこからがダメなのか
- なぜ止めるのか
- 親の気持ちはどうか
- 他者はどんなふうに感じるのか
これを穏やかに、しかし明確に伝えます。
◆ ポイント
- 一貫性(日によって対応を変えない)
- 短く具体的に(抽象説明は伝わりにくい)
- 境界は大人側が決める
子どもに判断を委ねすぎると、逆に負荷が大きすぎて不安定になります。
6. “叱らない子育て”の本当の危険性とは何か
それは、
子どもが外界のルールを学ぶ機会が失われ、
自我境界が育たず、
最終的に家庭が不安定化する点にある。
叱る・制止する・線を引くことは、
子どもの心を守るための大切な発達支援です。
親が我慢して怒らないことが「優しさ」ではありません。
世界の法則性を教えることこそが、
子どもにとって最大の安心につながる のです。
おわりに
“叱らない育児”という言葉の “叱らない”だけ に着目してしまうと、
子どもの世界に必要な境界が見えにくくなってしまいます。
多くの場合、それは 「子どもを傷つけたくない」 という深い愛情から生まれた選択です。
けれど、その愛情が 境界の提示という重要な役割を奪ってしまう危険性 があることを、この記事ではお伝えしました。
臨床の現場で数多くのご家庭を拝見していると、
境界が欠けると、子どもの内側に“世界の地図”が育たず、結果として家庭全体が不安定化する
という共通の構造が浮かび上がってきます。
子どもの心は、優しさだけでは安定しません。
優しさと境界。
この二つがそろって初めて、子どもの発達は安心して進んでいくのだろうと思います。