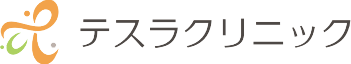リモートワークは“距離の問題”ではない——現場を知らずに語ることの危うさ
2025.10.05
近年、転職市場では「リモートワーク可」が働き方の前提条件のように語られることが増えました。
もちろん、リモート自体が悪いわけではありません。
むしろ、育児や介護、体調などの事情を抱えながらも働き続けられる手段として、リモート環境の整備は社会的に重要です。
ただし、私は一つだけ、どうしても引っかかることがあります。
「リモートワークを希望する人」が、一度も現場に足を運んだことがないままその働き方を前提にしているケースです。
そこには、距離そのものよりも深刻な問題——“現場への敬意の欠如”が潜んでいると感じます。
■ 「現場」は単なる作業場所ではない
私は精神科医として、日々、診察室で人と向き合っています。
患者さんの言葉は、文面だけを読んでも意味を成しません。
声のトーン、沈黙の長さ、目の動き——その“間”にこそ、最も大事な情報が隠れている。
同じように、どんな職種であっても「現場」には、言葉にならない“文脈”が流れています。
作業効率やタスク管理では拾いきれない、暗黙知や関係性のダイナミクスです。
それを知らずにリモートで仕事を完結させようとするのは、まるで患者を診ずにカルテだけで診断を下す医者のようなものです。
■ 上流と下流のナラティブを知らずに仕事はできない
現場を経験せずに働く人の多くは、自分の仕事の“前後”を想像しにくい。
たとえば、企画職が営業現場を知らずに戦略を立てれば、数字は整っても魂が抜ける。
逆に、オペレーション側が経営の視座を理解しなければ、効率化は単なる消耗戦になる。
リモートが成立するのは、上流と下流の物語を行き来できる人だけです。
それは「現場を知る」という単純な経験の積み重ねに他なりません。
■ 距離をとることは悪ではない。ただし、物語を共有しているなら。
私は、リモートワークを否定したいわけではありません。
むしろ、信頼が構築され、ナラティブを共有できているチームにおいては、
物理的な距離がある方が、創造的な対話が生まれることすらあります。
問題は、“距離をとること”ではなく、“物語を共有せずに距離をとること”です。
現場に立ったことのない人が、現場を想像せずに働くと、
そこに生まれるのは「効率化」ではなく「断絶」です。
■ 結び:「現場を尊重できる距離」を選ぼう
これからの時代、リモートかオフィスかという二項対立は意味を失っていくでしょう。
問うべきは、
「あなたは、どのくらい現場を理解してから距離をとりますか?」
ということです。
リモートとは“距離の取り方”ではなく、関係性の設計そのものです。
現場を一度でも見たことのある人だけが、
その距離の取り方を成熟したものにできる。
だから私は今も、「現場を知らないままリモートを語る」ことにだけは、
静かな違和感を覚えるのです。