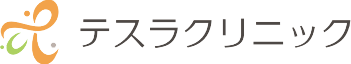発達障害の診断基準に載らない“しんどさ”とは?|APD・DCDなど当事者の意外な困りごと
2025.11.26
発達障害の診断基準には載らないのに、多くの当事者が「これが一番しんどい」と感じる現象を解説します。APD・DCDなどの特性や、検査では捉えにくい日常の困りごとを丁寧に整理し、理解を深めるためのポイントを紹介します。
はじめに
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)にはDSM-5という明確な診断基準があります。
しかし臨床の現場では、診断基準には書かれていないのに、当事者の多くが共通して経験している“生活上の困りごと” が少なくありません。
むしろ、こうした“基準外の症状”こそが、日常生活の質を大きく左右することがあります。
この記事では、医療機関での支援経験と当事者の語りの両方から、代表的な現象を整理していきます。
1|聴覚情報の「抜け落ち」:APD(聴覚情報処理の困難)
「声は聞こえているのに、意味が届かない」
「複数人の会話になると、会話に入れない」
こうした訴えは非常に多いものの、APD(Auditory Processing Difficulties)という概念はDSM-5の診断基準には含まれていません。
典型例は以下のようなものです。
- 騒がしい空間で会話が分からなくなる
- 相手の言葉が“音のまま”で、意味処理が追いつかない
- 会議や授業で指示を聞き逃しやすい
診断名というよりも、“脳の情報処理の特性の一つ”と捉えたほうが理解しやすい領域です。
2|手先や身体のぎこちなさ:DCD(発達性協調運動障害)
DCDもDSM-5では独立した診断名ですが、ASDやADHDの方が周辺的に持っているケース が多く見られます。
生活ではこんな困りごととして現れます。
- 靴ひもがうまく結べない
- 人と歩くとつい“かかとを踏んでしまう”
- ボールの距離感がつかめない
- 大人でも字を書くとすぐ手が疲れる
学校生活や仕事の細かな場面でストレスとして蓄積しやすい領域です。
3|診断基準には書かれないけれど圧倒的に多い日常の困りごと
以下はDSM-5のASD・ADHD基準には明記されていませんが、当事者の多くが訴える“典型的な周辺症状”です。
(1)時間感覚のズレ(タイム・ブラインドネス)
- 5分の感覚が人より長く/短く感じる
- 締め切りが近づいても実感が湧かない
- “未来の自分”を想像しにくい
ADHDの実行機能の弱さと関連します。
(2)刺激の「選別」が苦手
- 騒音・光・匂いなどの複数刺激を同時に処理すると負荷が跳ね上がる
- 図書館は得意だが、オープンスペースは苦手
- 会話と周囲の雑音が混ざって聞こえてしまう
ASDの感覚処理特性とも重なる部分です。
(3)マルチタスクで“思考が止まる”
- 作業と会話を同時にすると処理が破綻する
- 順番を切り替えようとした瞬間に固まる
- 頭が真っ白になり、言葉が出ない
「フリーズ」と表現される場合もあります。
(4)感情の“名前が分からない”:アレキシサイミア
- 自分の感情がよく分からない
- 身体症状として先に出る(頭痛、動悸、胃の痛みなど)
- カウンセリングで何を話したらいいのか分からない
当事者では非常によく見られる特徴です。
(5)表情・距離感の微妙な読み違い
- 相手の表情を“読みすぎる”
- またはほとんど拾えない
- 人との距離感がうまくつかめず、近すぎたり遠すぎたりする
社会生活に出てから悩みとして表面化しやすいテーマです。
(6)“スイッチが入らない”状態
- 必要なことほど、手がつかない
- やる気の問題ではなく、脳の実行機能が働きにくい
- 特にストレス状況では顕著
ADHDの特徴として語られますが、診断基準には含まれません。
4|これらは“病気の症状”か?
結論からいうと、多くは脳の情報処理の特性 であり、
「病気だから起こる現象」ではありません。
発達障害の診断基準は、生活での困難を説明するための“フレーム”に過ぎません。
実際の生活では、もっと多彩で個別的な現象が現れます。
そのため、支援には次のような視点が不可欠です。
- 個々の特性に合わせた環境調整
- 過度な刺激を減らす工夫
- タスクの構造化
- 音声より文字情報で補う方式
- 行動と感情の可視化
「診断名」よりも「生活の困りごと」を中心に支援する方が実践的です。
5|おわりに
診断基準に載らない困りごとは、本人にも周囲にも理解されにくいものです。
しかし、当事者の語りを丁寧に聴くと、そこに共通したパターンが多く存在します。
発達障害は“診断名”ではなく、脳の情報処理の多様性として理解することで、
日常生活の工夫や支援の方向がぐっと見えやすくなります。